目次
バリューエンジニアリングとは?
バリューエンジニアリング(Value Engineering、VE:価値工学)とは、製品やサービスの「価値」を「機能」と「コスト」との関係で捉え、価値を高める手法です。バリューアナリシス(Value Analysis、VA:価値分析)とも呼ばれています。製造業においては、設計段階でのデザインや製品改良、金型設計や製造方法を考える場面などで用いられます。
バリューエンジニアリングにおける価値、機能、コストの関係は、以下の式によって表されます。
価値=機能÷コスト
すなわち、価値を高めるために考えられるアプローチは、おおまかに以下の3つです。
- 同じコストで機能を高める
- 同じ機能でコストを抑える
- 低コストで大きく機能を向上させる
いずれにせよ、対象の価値が最も高くなるように、体系的・組織的に実践していくのがバリューエンジニアリングのポイントです。
機能とコストの定義について

では、具体的に「機能」や「コスト」は何を指しているのでしょうか。
バリューエンジニアリングに必要な前提として、それぞれの定義を確認しておきましょう。
機能:顧客の要求や期待に応えうるもの
バリューエンジニアリングにおける「機能」とは、製品・サービスに備わっていて、顧客の要求や期待に応えうるもの全般です。例えば、操作性や利便性を高めるタッチパッド機能や、安全性を高めるブザー機能、耐候性を高める防水機能などが挙げられます。備えられる機能の中でも、顧客にとってそれが必要か否かを判断し、可能な限り過剰機能を避け、不足機能を補うのがポイントです。
コスト:ライフサイクルコスト
バリューエンジニアリングにおける「コスト」とは、製品やサービスのライフサイクルのすべてにわたって発生する「総費用(ライフサイクルコスト)」です。
ライフサイクルを構成する段階は、企画・研究開発といったエンジニアリングチェーンから、調達・製造・流通といったサプライチェーン、アフターサービスや廃棄といった末端工程まですべて含みます。
各工程では大小問わず、時間・人員・資金といったコストが生じるため、これを把握・整理するのがコスト削減に至るために重要となります。
関連記事:エンジニアリングチェーンで製造業を変革する。サプライチェーンとの関係は?
関連記事:製造業界必須の知識、サプライチェーンマネジメントとは?
バリューエンジニアリングの進め方
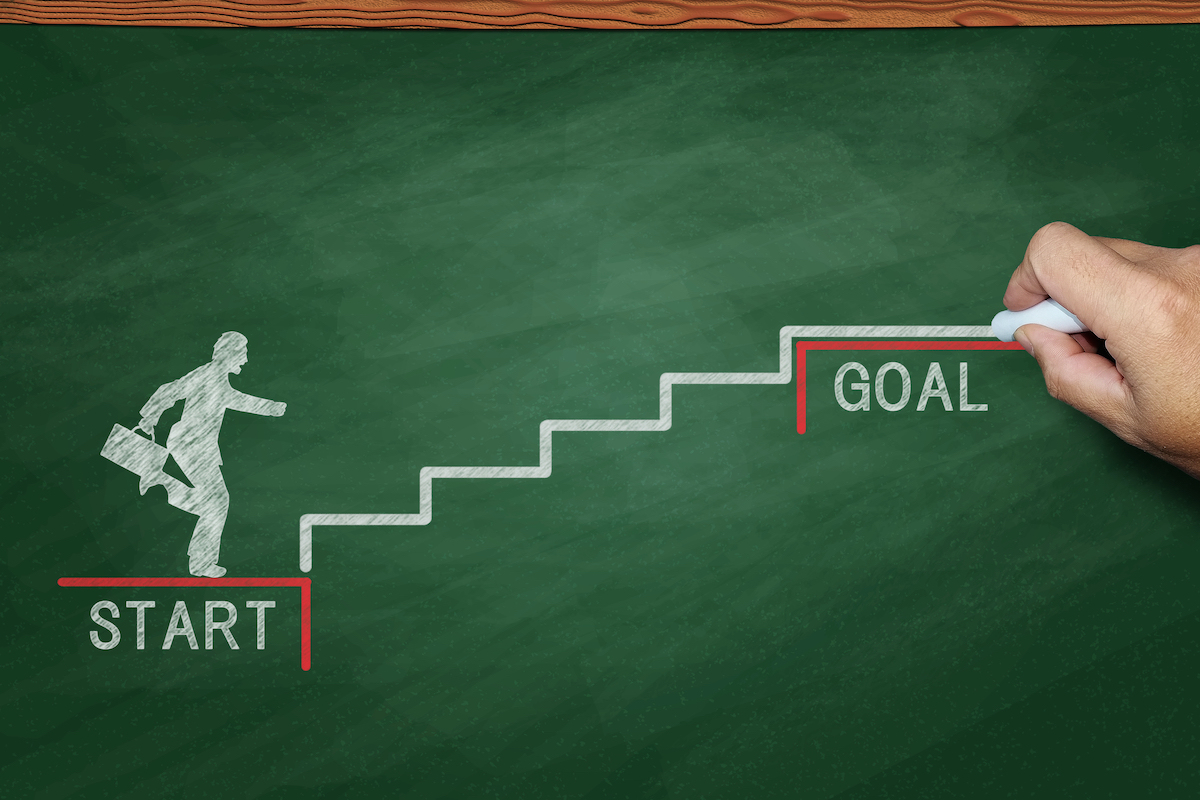
バリューエンジニアリングを効果的に進めるため、手順解説の前に押さえるべき要素を解説します。
まず、以下5つの観点を持っておきましょう。
| 観点 | 概要 |
|---|---|
| 使用者優先 | ユーザーの立場で、何を必要としているか追及する |
| 機能本位 | 思考の原点を機能に置き、製品・サービスを機能から評価する |
| アイデア発想 | 固定概念にとらわれず、新しい発想で工夫する |
| チームデザイン | さまざまな立場のメンバーの知識と技術を結集し、チームで改善する |
| 相関分析 | 機能とコストの相関を分析し、価値が最も高まるアプローチを探る |
では次に、大枠での手順を挙げていきます。
1.対象製品・サービスの情報収集
まず、チームメンバーが対象製品・サービスに精通し、共通の基盤に立つため、対象の使用・販売・設計・調達・製造・コストなどに関する情報を収集します。
2.機能の定義
続いて、機能を評価してアイデアを出すために、対象から機能を抽出して定義します。対象の構成要素から、働き・役割・目的を使用者目線で洗い出すのがポイントです。
3.機能別コスト分析
機能を定義して類型化できたら、必要とする機能の達成に費やされるコストを算出します。先ほど解説したコストの定義にしたがって、対象の構成要素やライフサイクルで生じるコストが、各機能にどれだけ関連しているかを明確にしておきます。
4.機能の評価
情報や分析結果が集まったら、各機能の価値の度合いを評価します。評価の基準は、機能達成に必要なコストの最低値(機能評価値)です。
機能評価値は、主に自社製品や競合他社の製品などの市場情報から適切に設定し、機能の重要度や実現可能性で重みづけしながら、評価の高い機能を採用します。
5.アイデア発想
調査・評価の次は、特定の機能を達成するためのアイデアを出していきます。この手順では、機能系統図を作成して、機能を構造化するのが重要です。
構造化は、機能における目的と手段で親子関係を作ることにより成立します。
機能系統図をボールペンで例えると、以下のような関係ができます。
字を書く(最上位目的)
→インクを芯から出す(手段/目的)
→芯の先に圧力がかかるときだけインクを出す(手段)
機能構造の中でも、なるべく上位機能に対してアイデア発想を行うのがポイントです。また、集団を生かせるブレーンストーミング法のような発想法が推奨されます。
6.具体化
最後のステップは、アイデアをもとにした、価値向上に寄与する代替案の具体化です。複数のアイデアを組み合わせたり、以下のサイクルを繰り返し回すことで、代替案は少しずつ詳細かつ現実的になっていきます。
- アイデアの利点・欠点分析
- 欠点の克服
- 洗練化
最終的には、投資対効果や技術性の評価を行い、その代替案が価値を向上させる内容か否かを確定させます。
バリューエンジニアリングの事例
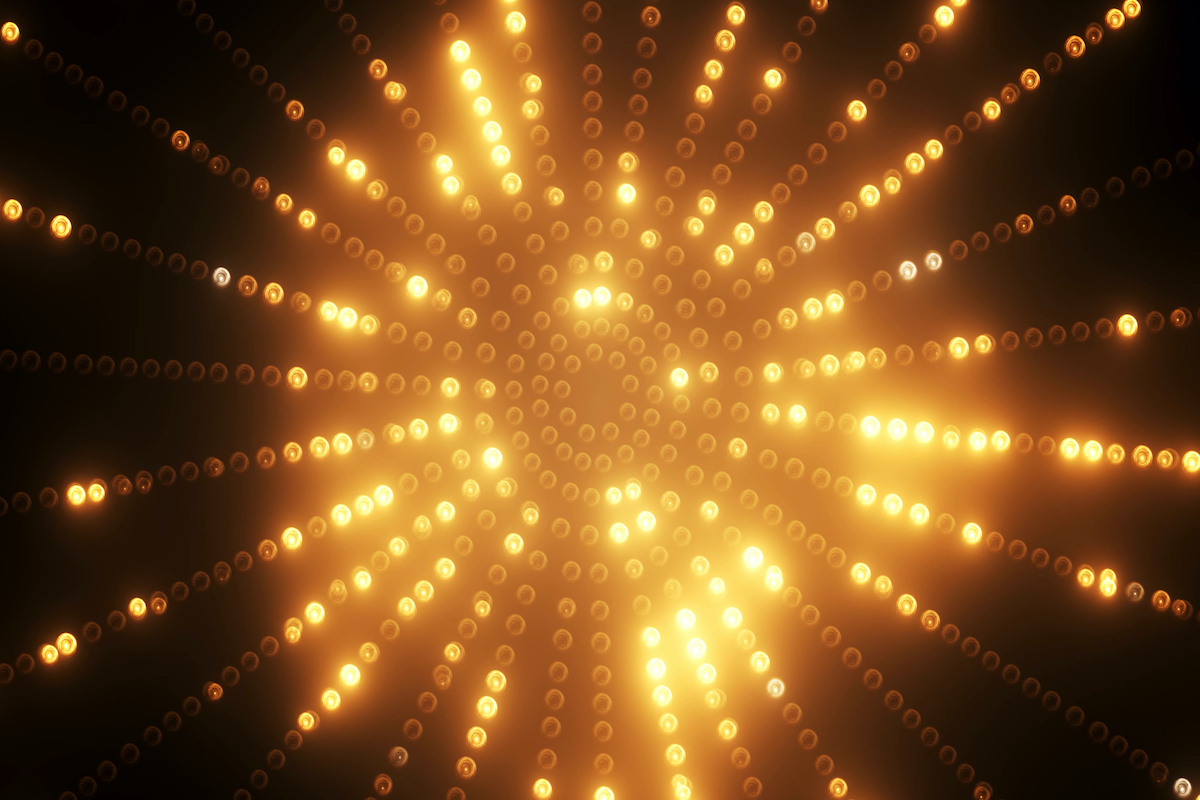
バリューエンジニアリングを活用して生まれた製品や工法について、3つの事例をご紹介します。
信号機のLED化
バリューエンジニアリングの成果が身近に確認できる例に、信号機のLED化が挙げられます。
信号機には、まず「交通を制御する」という最大の目的から、「色を伝える」という機能、そしてさらに「光を発生する」という機能が付随します。
メーカーが改良の際に着目したのは、「光を発生する機能」です。従来の白熱電球より、光の指向性や寿命の点で優れるLEDを光源に採用することで、視認性が向上し、ランニングコストや保守費が削減されました。
ユニット締結用ネジを減らす設計
大量生産品での開発設計過程では、機能追加や改善のために部品を追加することがありますが、これが積み重なると当初の予定材料費をオーバーする可能性もあります。
そこで、機能を維持しながら部品点数を削減した設計という形でバリューエンジニアリングを図ります。よく採用されるのが、ユニット締結用ネジの削減です。リベット締めやスポット溶接といった他の締結方法を、材料に合わせて適切に選択すれば、材料費を安価に抑えられます。
産業機械のメンテナンスフリー期間延長
工場内の製造で使われる産業機械は、稼働を続けるうちに摩耗し、故障率が高まっていくため、定期的にメンテナンスする必要があります。そこで、可能な限りメンテナンスフリーの期間を長く確保できれば、保守費の削減になります。例えば、以下のような工夫が有効と言えるでしょう。
- 熱炉出口コンベヤ用のベアリングユニットに耐熱グリースを塗り、熱による劣化を防ぐ
- 部品搬送中に洗浄液にさらされる金属製ローラーをウレタン製に換装し、機構を長寿化する
価値を向上させるために継続的な実践活動を
バリューエンジニアリングには、機能や仕様の開発を重視するアプローチと、コストダウンを狙うアプローチのふたつがあります。
いずれも製品・サービスの価値向上という1点を目指すシンプルな理論ですが、実現に至るまでの道のりは長く複雑です。さらに実現後の価値は、実務への適用後に効果を生み出して初めて評価されます。
すなわちバリューエンジニアリングは、理論で固めるよりも実践を繰り返してこそ真価を発揮します。実践の過程で磨かれる創造力や手法・技法を蓄積し、事業活動の質を向上させていきましょう。



