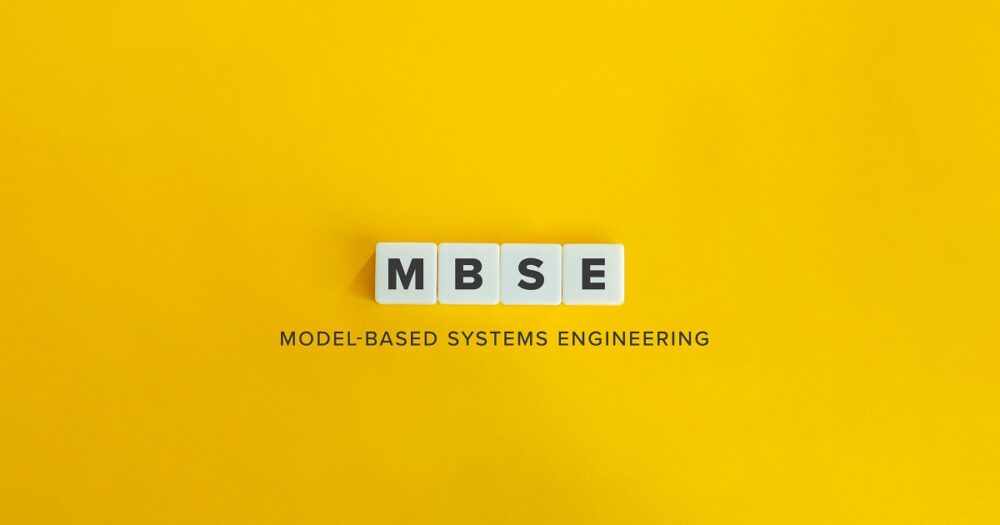目次
MBSE (モデルベースシステムズエンジニアリング)とは?基本知識と概念
MBSE(Model-Based Systems Engineering)は、前述したとおり、システムズエンジニアリングのプロセス全体をモデルによって実行する手法です。従来の文書ベースの設計手法とは根本的に異なり、システム全体を統一されたデジタルモデルで表現し、設計から検証まで一貫して管理します。
MBSEの基本概念とシステムズエンジニアリング
MBSEを理解するには、まずシステムズエンジニアリングの概念を把握する必要があります。システムズエンジニアリングとは、複雑なシステムを構成要素の相互関係まで含めて体系的に設計・開発・運用する工学分野です。自動車、航空機、産業機械などの現代の製品は、機械、電子、ソフトウェアが密接に連携する複合システムであり、従来の縦割りの設計手法では対応が困難になっています。
MBSEでは、SysML(Systems Modeling Language)などの標準化されたモデリング言語を使用し、要件定義から機能分析、アーキテクチャ設計、検証・妥当性確認まで、すべての工程をモデルベースで実行します。これにより、設計思想や技術仕様が関係者間で共有され、設計変更の影響範囲も即座に把握できるようになります。
従来手法との違いとデジタル化のメリット
従来のドキュメントベース設計では、要件仕様書、機能仕様書、設計仕様書などが個別に作成され、それぞれの整合性を保つことが困難でした。設計変更が発生すると、関連する複数の文書を手動で更新する必要があり、ヒューマンエラーや情報の不整合が発生しやすい状況でした。
MBSEでは、中心となるシステムモデルから各種の成果物を自動生成するため、一元的な情報管理と整合性の確保が可能になります。また、モデルは実行可能であり、設計段階でのシミュレーションによる早期検証が実現できます。これにより、後工程での設計不具合の発見と修正コストを大幅に削減できます。
MBSEツールとSysMLの活用
MBSEの実践には専用のツールとモデリング言語が必要です。主要なMBSEツールは、SysMLに対応し、要件管理からアーキテクチャ設計まで統合的な環境を提供します。
SysMLは、システムズエンジニアリング専用に開発されたモデリング言語で、要件図、ユースケース図、アクティビティ図、シーケンス図、状態マシン図、ブロック定義図、内部ブロック図、パラメトリック図、パッケージ図の9種類の図表でシステムを表現します。これにより、システムの構造、振る舞い、要件、制約を包括的にモデル化できます。以下には、主な4つの図表とその用途、それぞれが特定のシステム要素を表現する内容が示されています。
| SysML図表 | 用途 | 表現内容 |
|---|---|---|
| 要件図 | 要件の構造化 | システムに対する要求と関連性 |
| ユースケース図 | 機能要件の整理 | システムの利用シナリオ |
| アクティビティ図 | プロセスの可視化 | システムの動作フロー |
| ブロック定義図 | システム構造 | コンポーネントと関係性 |
MBSEとMBDの違いと関係性
製造業のデジタル化において、MBSEと並んでよく耳にするのがMBD(Model-Based Development:モデルベース開発)です。両者は「モデルベース」という共通点を持ちながら、対象範囲や目的が大きく異なります。正しい理解と使い分けが、効果的な導入の鍵となります。
MBDの概要と特徴
MBDは、主にソフトウェア開発やコントローラー開発において、数学モデルやシミュレーションモデルを用いて設計・開発を行う手法です。MBDは具体的な制御アルゴリズムや物理現象をモデル化し、シミュレーションによる検証と自動コード生成を通じて開発効率を向上させるのが主目的です。
主要なMBDツールは、制御システムの設計からC/C++コードの自動生成まで対応し、組み込みシステム開発において広く普及しています。特に自動車業界では、ECU(Electronic Control Unit)の開発において標準的な手法となっています。
MBSEとMBDの適用範囲と目的の違い
MBSEとMBDの最も大きな違いは、適用範囲と目的にあります。MBDが主に制御ソフトウェアやアルゴリズムの開発効率向上を目指すのに対し、MBSEはシステム全体のライフサイクル管理を対象とします。
MBSEは、顧客要件の分析から始まり、システムアーキテクチャの設計、サブシステムの仕様策定、検証・妥当性確認まで、システム開発の全工程を統合的に管理します。一方、MBDは既に決定されたシステム仕様に基づいて、具体的な制御アルゴリズムを効率的に実装することに特化しています。
例えば、自動車の自動ブレーキシステムを開発する場合、MBSEではセンサー配置、制動力配分、HMI設計、安全要件まで含めたシステム全体を設計します。MBDでは、MBSEで決定されたアーキテクチャに基づいて、ブレーキ制御アルゴリズムを実装し、シミュレーションで性能を検証します。
MBSEとMBDの相互補完関係と統合的活用
MBSEとMBDは対立する概念ではなく、むしろ相互補完的な関係にあります。MBSEで策定したシステムアーキテクチャに基づき、MBDで具体的な制御系を効率的に開発するという連携が理想的です。
実際の開発プロセスでは、MBSEによるシステム設計フェーズでサブシステム間のインターフェースや制約条件を明確に定義し、その情報をMBDツールに引き継ぐことで、一貫性のある開発が可能になります。また、MBDで作成されたシミュレーションモデルの結果をMBSEモデルにフィードバックすることで、システム全体の検証精度も向上します。以下に、MBSEとMBDの比較を示します。
| 比較項目 | MBSE | MBD |
|---|---|---|
| 主目的 | システム全体の統合設計 | 制御アルゴリズムの効率開発 |
| 対象範囲 | 要件分析〜運用・保守 | 詳細設計〜実装・テスト |
| モデル言語 | SysML、UAF等 | Simulink、Stateflow等 |
| 成果物 | 要件、アーキテクチャ、仕様 | 実行可能コード、テストケース |
| 適用分野 | 全業界のシステム開発 | 組み込み制御システム |
製造業でMBSEが注目される理由
製造業において、MBSEへの注目が急速に高まっている背景には、市場環境の変化と技術的課題の複雑化があります。従来の開発手法では対応困難な課題を解決する手段として、MBSEが期待されています。
製品複雑化への対応とシステム統合の必要性
現代の製造業製品は、機械、電子、ソフトウェアが密接に連携するサイバーフィジカルシステム(CPS)へと進化しています。自動車業界を例にとると、1台の車両に搭載されるECUは100個以上に達し、それらが協調して動作する必要があります。
MBSEは、このような複雑なシステムの相互依存関係を可視化し、全体最適の観点から設計を進められるため、従来の部分最適による問題を解決できます。また、システムレベルでの早期検証により、後工程での大幅な設計変更を防止し、開発リスクを低減します。
航空宇宙産業では、さらに高い信頼性と安全性が要求されます。最新航空機では、数百万行のソフトウェアコードが機体システムを制御しており、MBSEなしには開発が不可能な状況となっています。
開発スピード向上と市場要求への迅速な対応
グローバル競争が激化する中、製品の市場投入スピードは競争優位性を左右する重要な要素となっています。特に自動車業界では、電動化、自動化、コネクテッド化といった技術革新への対応スピードが企業の命運を分けています。
MBSEによるモデルベース設計では、設計変更の影響範囲を瞬時に把握でき、関連する成果物の自動更新が可能です。これにより、従来は数週間を要した設計変更対応が数日で完了し、開発リードタイムの大幅短縮を実現できます。また、バーチャルプロトタイプによる早期検証により、物理試作回数を削減し、開発コストの低減も同時に達成できます。
多様な人材の連携強化と情報共有の効率化
現代の製品開発は、機械、電子、ソフトウェア、制御など多岐にわたる専門分野の技術者が連携して進める必要があります。しかし、各分野には固有の専門用語や設計手法があり、分野間のコミュニケーションが困難な場合が多くありました。
MBSEでは、SysMLという標準化されたモデリング言語を使用することで、異なる専門分野の技術者間での情報共有が円滑になり、設計思想の統一が図れます。また、モデルは視覚的であり、文書ベースの仕様書よりも理解しやすいため、新入社員や異分野からの転入者への知識移転も効率的に行えます。
さらに、リモートワークが普及した現在、地理的に分散したチームでの共同開発においても、クラウドベースのMBSEツールを活用することで、リアルタイムでの情報共有と協働作業が可能になっています。以下は、MBSEの導入による具体的な利点になります。
- 設計情報の一元管理により、バージョン管理と更新履歴の追跡が自動化
- 要件変更から実装への影響分析が瞬時に実行可能
- マルチドメインシミュレーションによる統合検証環境の構築
- 国際標準規格への準拠支援機能
MBSE導入の成功事例と具体例
MBSEの理論的メリットを理解しても、実際の現場でどのような効果が得られるかが最も重要な関心事です。ここでは、国内外の代表的な製造業企業におけるMBSE導入事例を通じて、具体的な成果と導入のポイントを詳しく解説します。
自動車業界での導入事例と効果
自動車業界は、MBSEの導入が進んでいる分野の一つです。ある自動車メーカーでは、電動車両の開発においてMBSEを全面的に採用し、開発期間の短縮に成功しました。
このプロジェクトでは、バッテリーマネジメントシステム、モーター制御、回生ブレーキなどの複雑な電動化技術をMBSEによって統合的に設計することで、サブシステム間の最適化を実現しました。特に、従来は物理試作で検証していた熱管理システムを、マルチフィジクスシミュレーションで事前に検証することにより、試作コストの大幅削減が可能となりました。
別の自動車メーカーでは、先進運転支援システム(ADAS)の開発においてMBSEを活用し、機能安全規格への準拠を効率化しています。要件から実装までのトレーサビリティをMBSEモデルで管理することで、安全分析にかかる工数や認証取得までの期間を短縮しています。
航空宇宙産業における大規模システム開発事例
航空宇宙産業では、膨大な部品と複雑に相互接続されたシステムを、安全性を確保しながら限られた期間で統合することが求められます。ある航空機開発プロジェクトでは、機体システム、エンジン制御、アビオニクス、客室システムなど、多岐にわたる領域を単一のMBSEモデル上で統合管理しました。
これにより、従来は部門ごとに進められていた設計作業がモデル上で可視化され、設計変更の影響を迅速に把握できるようになりました。その結果、調整に要する期間が短縮され、プロジェクト全体の進行が円滑になりました。さらに、国際的な安全規格への準拠プロセスも効率化され、認証準備を計画的に進められるようになりました。
この事例は、MBSEが単なる設計支援ツールにとどまらず、複雑な開発現場を結びつける共通基盤として機能することを示しています。
産業機械・ロボット分野での活用例
産業機械分野でも、IoT化とスマートファクトリー化の進展に伴い、MBSEの導入が加速しています。ドイツの産業用ロボットメーカーでは、協働ロボット(コボット)の開発にMBSEを適用し、安全性と性能の両立を実現しています。
このプロジェクトでは、人間とロボットが同じ作業空間で協働する環境を想定し、安全要件を詳細にモデル化。センサーフュージョン、力制御、緊急停止システムなどを統合的に設計しました。MBSEによるシステムレベルでの早期検証により、安全認証取得までの期間を短縮し、市場投入のスピード向上につなげています。
国内の産業機械メーカーでも、工作機械のデジタルツイン構築においてMBSEを活用し、予知保全システムの開発効率を向上させている事例があります。物理モデルとデジタルモデルの整合性をMBSEで管理することで、現実とデジタル空間の同期精度を高め、予知保全の精度向上を実現しています。
MBSE導入の課題と成功のポイント
MBSEの導入は多くのメリットをもたらす一方で、組織変革を伴う大きなチャレンジでもあります。成功している企業と失敗する企業の違いを分析し、実践的な導入アプローチを整理します。
導入時の主な障壁と対策
MBSE導入における最大の障壁は、従来の働き方からの変革への抵抗です。長年培ってきたドキュメントベースの設計手法から、モデルベースの手法への転換は、技術者にとって大きな負担となります。
導入に成功した企業では、まず小規模なパイロットプロジェクトでMBSEの効果を実証し、成功体験を組織内で共有することから始めています。急激な全社導入ではなく、段階的なアプローチを取ることで、現場の理解と協力を得やすくなります。
また、技術面では、既存のPLMシステムやCADツールとの連携が課題となります。MBSEツールが孤立してしまうと、かえって業務効率が悪化する可能性があります。事前にシステム間のデータ連携方式を検討し、統合的なデジタル環境を構築することが重要です。
組織体制と人材育成の重要性
MBSEの導入は技術導入にとどまらず、組織全体の業務プロセス変革を伴います。成功企業では、経営層のコミットメントのもと、専門組織を設置してMBSE導入を推進しています。
人材育成においては、単なるツールの使い方の習得ではなく、システムズエンジニアリングの思考法から教育することが重要です。外部研修の受講、専門資格の取得支援、社内エキスパートの育成など、中長期的な人材開発戦略が必要です。
特に重要なのは、MBSEチャンピオンとなる人材を各部門に配置し、現場レベルでの普及促進を図ることです。技術的な専門性と併せて、部門間の調整能力を持つ人材が、導入成功の鍵を握ります。
段階的導入アプローチとROIの確保
MBSE導入の投資対効果を確実に得るためには、戦略的な段階的アプローチが不可欠です。成功した企業の多くでは、「学習フェーズ」「実証フェーズ」「展開フェーズ」の3段階で導入を進めています。
学習フェーズでは、小規模なプロトタイププロジェクトを通じて、組織としてのMBSEの理解を深めます。実証フェーズでは、実際の製品開発プロジェクトでMBSEを適用し、定量的な効果測定を行います。展開フェーズでは、得られた知見をもとに、全社的な標準プロセスとして確立します。
ROI確保のためには、導入効果を適切に測定・評価する仕組みが必要です。開発期間短縮、品質向上、コスト削減などの定量指標に加え、技術者のモチベーション向上や知識共有の促進などの定性的効果も併せて評価することが重要です。以下の要素を取り入れた段階的アプローチが成功につながります。
- 経営層による明確なビジョン設定と継続的なコミットメント
- 既存システムとの統合を考慮したツール選定と環境構築
- 現場主導による段階的な展開と成功事例の蓄積
- 専門人材の育成と外部パートナーとの協業体制の構築
- 定量・定性両面での効果測定と継続的な改善プロセス
まとめ
MBSEは、複雑化する製造業の製品開発において、システム全体を統合的に設計・管理する革新的な手法です。MBDが制御アルゴリズムの効率的な実装に特化するのに対し、MBSEは要件分析からライフサイクル全体を通じたシステムマネジメントを担います。
製造業でMBSEが注目される背景には、製品の複雑化、開発スピードの要求、多様な人材連携の必要性があります。自動車、航空宇宙、産業機械分野での成功事例は、開発期間短縮、品質向上、コスト削減といった具体的な効果を実証しています。
導入を成功させるためには、段階的なアプローチと組織的なコミットメントが不可欠です。技術導入にとどまらず、業務プロセスの変革と人材育成を並行して進めることで、MBSEの真価を発揮できます。製造業のデジタル変革において、MBSEは競争優位性を確保する重要な戦略ツールとなるでしょう。
参考文献
https://www.cct-inc.co.jp/koto-online/archives/155