目次
近年はITの発展が目覚ましく、AI(人工知能)やIoT(モノのインターネット)、ビッグデータなど、情報を潤沢にいかした次世代技術の産業化は黎明期に入ったといえるでしょう。
同時に、さらなる次世代技術の研究・開発も水面下で進んでおり、なかでもIoE(あらゆるモノのインターネット)が先に控えているといわれています。
IoEの対象には人間も含まれるとされ、「人と機械を直接的につなぐ」ところまで議論が進んでいるのです。
本記事では、人の脳と機械をつなぐ技術「BMI(ブレイン・マシン・インターフェース)」について、その概要や実現方法、世界各国の政策・投資動向からBMIとVRを組み合わせたソリューションまで解説します。
BMI(ブレイン・マシン・インターフェース)とは?

BMI(Brain machine Interface:ブレイン・マシン・インタフェース)とは、脳(ブレイン)と機械(マシン)をつなぐ(インターフェース)技術や機器の総称です。
脳とコンピュータをつなぐ場合には、BCI(Brain Computer Interface:ブレイン・コンピュータ・インターフェース)と呼ぶ場合がありますが、本稿ではBCIの定義もふくめてBMIと呼称します。
BMIによって脳と機械の間を電気信号でやり取りすることで、機械が脳へ干渉したり、脳が機械へ直接指示を出したりなどの意思疎通が可能になるといわれています。
これは空想上の話ではなく、社会実装を前提とした研究が進められている科学技術の一分野です。
BMIの実用可能性について
人間の知的活動や身体活動は、脳が担う認識・学習・決定などの高度な情報処理が可能としています。
このことから、BMIは人間の脳から情報を取り出して何かに活用したり、人間の脳に情報を与えて欠落した機能を補完したりできる可能性を秘めているのです。
この可能性を模索する研究分野は「ニューロテクノロジー(脳情報科学)」と呼ばれ、言葉にできない知識である「暗黙知」をビジネスに利用したり、体の不自由な方のリハビリに利用したりと、社会にとって利のある使い道が考えられています。
近年の脳活動測定技術やAI(人工知能)による分析技術の進歩であったり、世界各国で発足する研究プロジェクトなどにより、BMIの研究は進展を見せており、社会的な注目は非常に高いといえるでしょう。
BMIで脳と機械はどのようにつながるのか?
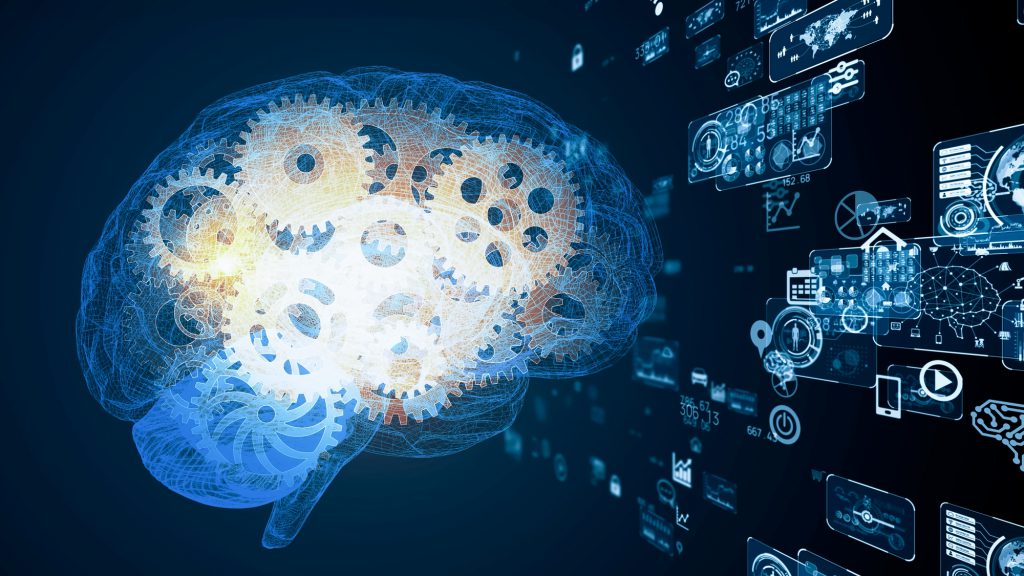
現時点で想定されている脳と機械をつなげる方法はふたつあります。
ひとつめは、外科手術によって頭蓋に電極を埋め込む「侵襲(しんしゅう)式」です。患者に身体的負荷がかかる分、膨大なニューロン(脳神経)活動をリアルタイムに処理できるため、得られる情報や接続先の機械を操作する際の精度は高いレベルのものが期待されます。
ふたつめは、開頭手術を行わず、センサーを取り付けたヘッドギアなどを利用して頭皮から脳情報を得る「非侵襲式」です。身体的負荷がかからないため、さまざまなサービスやソリューションに活用しやすく、一般社会に流通しやすい方法となるでしょう。
また、BMIはやり取りする情報の向き先によって「入力型」「介入型」「出力型」の3種類に分類できます。
入力型BMI
入力型BMIは、機械から脳に向かって情報を送るタイプの技術です。すでに医療の分野では侵襲式の実用例があり、蝸牛(音の情報を電気信号に変換する内耳器官)の代わりに機械を埋め込み、直接神経を刺激して脳へ電気信号を送る「人工内耳」が代表例として挙げられます。
介入型BMI
介入型BMIは、すでに行われている脳の情報処理や神経信号の伝達に対し、文字通り介入するタイプの技術です。すでにパーキンソン病などの運動障害に関する臨床事例があり、異常のある特定の脳の部位に電気刺激を与えるなど、意図的に介入することで脳機能を調整する「深部脳刺激(DBS)」が代表例です。
出力型BMI
出力型BMIは、脳波を外部に出力するタイプの技術です。現時点での入力型や介入型は身体機能補助の応用事例が多い一方、出力型の場合はあらゆる活用方法が考えられます。
たとえば、脳波をトリガーとしたロボット操作やゲーム操作を競技として行う「b(BRAIN)スポーツ」や、発話や筆談などが困難な方々が頭のなかで考えただけで内容を言語化する新しいコミュニケーション方法など、現段階でさまざまな構想があります。
出力型BMIの実用例は確認されておらず、実現させるためには主に次のような技術が成熟する必要があるといわれています。
- デコーディング: 脳活動パターンから主観的な意識や知覚の解読を可能にする技術
- ニューロフィードバック: 脳活動をリアルタイムにモニタリングし、脳活動を自己制御する技術
これが実現することで、これまで手足によって操作してきたものが、「念じる」だけで動かせる時代が訪れるのです。
BMIに関する政策や投資動向について
BMIの社会実装に向けた研究は世界各国で行われており、産官学連携のもと莫大な資金を投じた技術開発が進められています。
たとえば、アメリカの大規模脳研究計画「BRAIN Intiative」では10年間で45億ドル、EUのBMIデバイス開発プロジェクト「BNCI Horizon 2020」では7年間で800億ユーロの予算が投じられており、その重要性が伺えます。
日本においても、文部科学省が「脳科学研究推進戦略プログラム」を主導し、各省庁で研究開発事業を実施しています。
こうした政策にもとづいて大学などの機関が研究を進めつつ、最終的な製品・サービス化を担う民間企業がBMIに積極的な投資を行うという動きが活発化しているのです。
企業動向については、とくにアメリカや中国における初動が速く、すでに数社が実用化に向けた発表を行っています。
アメリカのFacebook(フェイスブック)社が開発中である「画面に触れずにSNSを操作可能なリストバンド型BMI」や、中国系スタートアップBrainCo社が発表した「人が見ているものや想像しているものを復元できるBMI」など、実現化の形はさまざまです。
BMIとVRを組み合わせたソリューションも
BMIの研究は、VR(仮想現実)におけるデジタル空間と組み合わせた活用についても注目されています。
国内の大きな動向としては、防衛医科大学校が「防衛装備庁技術シンポジウム2018」で展示した「VR模擬戦遂行時の脳波計測」が挙げられます。
この取り組みは、VR空間内で模擬戦を行う軍事教練シミュレータを使用し、銃撃の命中有無、あるいは被弾時などの脳波を取得し、隊員のレジリエンス(ストレス耐性やストレス反応からの回復力)を分析・強化する目的で行われたとのことです。
海外の代表事例では、2016年にVRスタートアップ初のユニコーン企業*となったスイスのMindMaze社が、脳に損傷を受けた患者の回復を目的とした医療用VR製品を開発し、世界中から注目を集めています。
同製品は脳イメージング、脳科学、VRなどを組み合わせ、VR空間で直感的なリハビリを可能としており、HMD含めたデバイスがすでに世界中の病院に配置され使用されています。
*評価額が10億ドル以上の未上場のスタートアップ企業
人が思うままにテクノロジーを扱う時代が近づいている
BMIの研究には、「脳と機械をつなげる」という技術的な観点と「脳と機械のつながりを活用する」という実用的な観点の2種類があります。
いずれも段階的に実現可能なソリューションとして発表・実用化がされており、主に医療分野における身体機能補助を目的とした応用事例は現時点で確認可能です。
今後研究が進んでいけば、思うだけで操作できるデバイスが市販化される時代もやってくるでしょう。
脳情報を活用する新しい産業も生まれる見込みも高く、社会が次なるステージへ進む瞬間には目が離せません。



