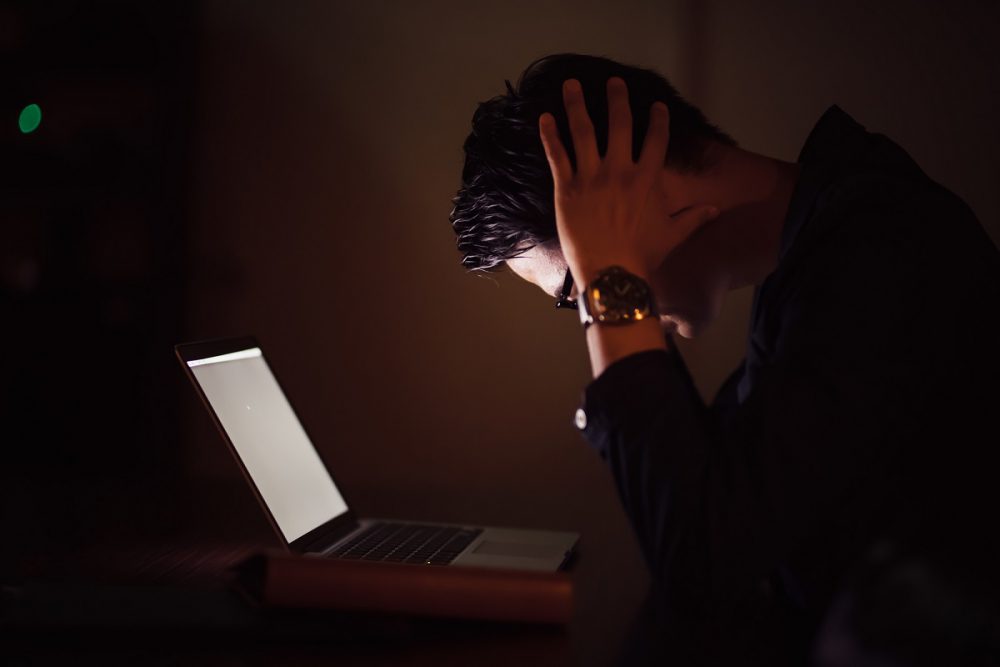目次
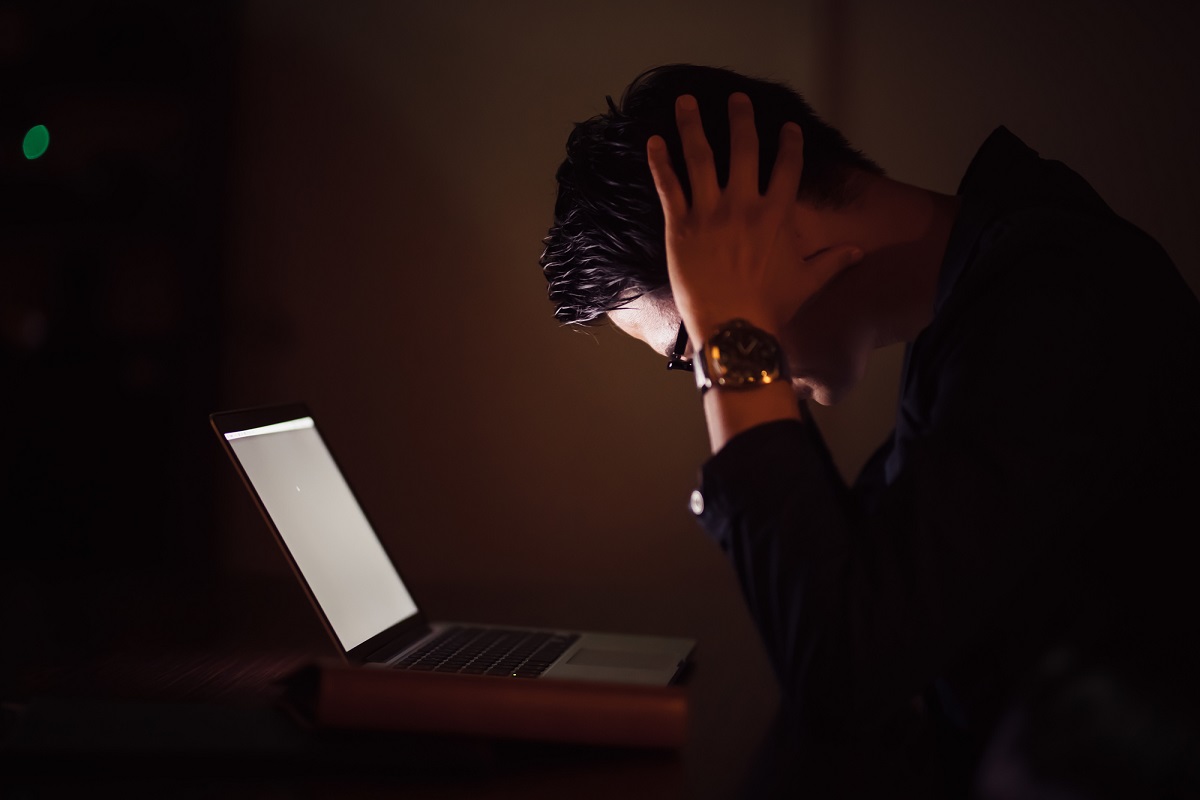 情報技術(IT)はここ数年で急速な進歩を遂げ、IT社会の次なる段階であるデジタル社会を迎える準備は万全のように見えます。しかし実際は、「2025年」を境に、国内IT産業の明暗を分けるレベルの深刻な課題が立ちはだかるのです。
今回は、その課題である「2025年の崖」問題についての概要や、製造業を含めた課題への対策について解説します。
情報技術(IT)はここ数年で急速な進歩を遂げ、IT社会の次なる段階であるデジタル社会を迎える準備は万全のように見えます。しかし実際は、「2025年」を境に、国内IT産業の明暗を分けるレベルの深刻な課題が立ちはだかるのです。
今回は、その課題である「2025年の崖」問題についての概要や、製造業を含めた課題への対策について解説します。
「2025年の崖」問題とは?
 「2025年の崖」問題とは、経済産業省が2018年に発表した「DXレポート」で登場する、ITに関する諸問題を指す言葉です。なおDX(デジタルトランスフォーメーション)とは、企業がデジタル技術に対応し、組織やビジネスモデルの変革を目指す一連の取り組みです。
「2025年の崖」問題の根幹となるのは、主にレガシーシステムと呼ばれる老朽化・複雑化・ブラックボックス化した旧世代の基幹系システムです。
ITシステムには、会社の事業活動を裏で支える基幹系システム(ERP)や、銀行の勘定系システムや製造業の生産管理システムといった業界特化型のシステムなどの分類があります。
こうしたシステムに関する問題について、経産省は「2025年」をキーワードに以下のような最悪のシナリオを想定しています。
「2025年の崖」問題とは、経済産業省が2018年に発表した「DXレポート」で登場する、ITに関する諸問題を指す言葉です。なおDX(デジタルトランスフォーメーション)とは、企業がデジタル技術に対応し、組織やビジネスモデルの変革を目指す一連の取り組みです。
「2025年の崖」問題の根幹となるのは、主にレガシーシステムと呼ばれる老朽化・複雑化・ブラックボックス化した旧世代の基幹系システムです。
ITシステムには、会社の事業活動を裏で支える基幹系システム(ERP)や、銀行の勘定系システムや製造業の生産管理システムといった業界特化型のシステムなどの分類があります。
こうしたシステムに関する問題について、経産省は「2025年」をキーワードに以下のような最悪のシナリオを想定しています。
1.レガシーシステムに要する工数の増加
現在稼働中のITシステムの中には、数十年前に古い言語や汎用機によって構築されたシステムも少なからず存在します。 当然ながら時間が経過すればするほど、当時のシステム開発に詳しいエンジニアは高齢化し、退職していきます。したがって技術ノウハウを持った人材が減少するのです。 つまり、レガシーシステムは運用・保守の難易度が高く、ひいては必要な作業量が多くなる傾向にあります。2.IT予算がレガシーシステムに吸い取られる
DXレポートによれば、IT人材は不足の一途を辿っており、不足するIT人材数は2015年の約17万人から2025年には約43万人まで拡大する見通しです。このような現状にもかかわらず、レガシーシステムに割く作業量の増加によって、貴重なIT人材はその運用・保守に駆り出されてしまいます。 経済産業省の予想では、このまま対策を取らなかった場合、2025年におけるIT予算の約9割がシステム維持管理費で占められるとのことです。3.世界規模のデジタル戦争に負けて大規模な経済損失に
近年、DX(デジタルトランスフォーメーション)という概念が社会に浸透し、これを実現する技術開発は世界中で行われています。 今後の日本の国際競争力は、DXを通したデジタル戦争をどう戦うかによって左右される部分も大きいでしょう。 しかし、もしレガシーシステムの維持という守りの投資によって、DXを実現する攻めの投資が落ち込んでしまった場合、デジタル戦争には敗北し、世界に大きく後れを取ることになります。 結果として2025年以降、現在の3倍となる年間最大12兆円の経済損失が生じる可能性が指摘されているのです。4.国内IT産業が永続的に低迷する
DX産業への参入失敗後も、IT人材ひいてはシステム運用・保守の担い手が減少し、既存システムの維持もままならなくなる最悪のリスクも考えられます。 システムが維持できなくなると、セキュリティ上の脆弱性が高まることに繋がります。 つまり、可用性や信頼性、完全性に欠けるサービスが増加していき、国内IT産業は永続的に低迷し続けていく可能性があります。 2025年までにレガシーシステムへの対策とDXへの投資が成功しない場合、崖から落ちるような国際競争力低下と莫大な経済損失が待っていると考えておくべきでしょう。 参照:「DX レポート (サマリー)」経済産業省なぜレガシーシステムが生まれるのか
 次に、日本の将来を蝕むレガシーシステムが生じてしまう具体的な原因について考えてみましょう。主に挙げられるのは以下の3点です。
次に、日本の将来を蝕むレガシーシステムが生じてしまう具体的な原因について考えてみましょう。主に挙げられるのは以下の3点です。
技術ノウハウがベンダーに集中しやすい
大規模なシステム部門あるいは専門の子会社を持つ企業でもない限り、ERPの導入は外部のベンダーに頼る必要があります。 ベンダーとは、システムを利用する会社(ユーザー)に対し、パッケージシステムの販売や、システム構築のサポートを行う会社(SlerやITコンサルなど)です。 システム担当者とベンダーは都度認識合わせをしながらシステム構築を進めますが、直接的に開発を担当するのはベンダー側です。 その場合、どうしてもIT自体の知識・スキルはもちろん、構築されたシステム機能の詳細な知識といった技術ノウハウはベンダーに集中します。 システムが本番稼働した後も、ベンダーは運用・保守の手順書やサポートメンバーを残すのが慣例ですが、こういった支援が薄くなるとシステム担当者が自社システムを詳しく知らない状態が横行しやすくなります。 そうなった場合、運用・保守の高いレガシーシステムが発生しやすくなるのです。技術ノウハウが属人化しやすい
システム開発のメンバーを個人レベルで見てみると各々が実際に手を動かす分野はそれぞれ細かく分かれます。 つまり、特定の機能に関する熟練度は個人によって差が生じ、技術ノウハウは属人化しやすい性質があります。 とりわけ機能詳細や設計意図などが特定のエンジニアが握られたまま、その人物が異動や退職によって現場を離れてしまうと、システムの一部はブラックボックス化します。 正しく引き継ぎを行わなければ、保守性が低下するだけでなく、ブラックボックスの解析という本来不要な業務にコストを投じなくてはならないのです。システムの更改にインセンティブが生じにくい
経産省の調査では、約8割の企業がレガシーシステムを抱えていることがわかっており、製造業も例外ではありません。 つまり、経営層が自社システムの問題を自覚していながら、システム更改に踏み切っていない企業が現状として多いのです。 原因として、経営層がレガシーシステムが引き起こす問題を軽視している可能性もありますが、それ以上に「システム更改にインセンティブが生じにくい」という事実が挙げられます。 一般的なシステム更改プロジェクトは年単位の時間を要し、費用は企業規模によっては数百億にのぼります。 したがって、現行システムの問題が顕在化していない内に、それだけ大規模なコストを投じられず、レガシーシステム対策への初動が遅れるリスクがあるのです。製造業における「2025年の崖」対策とは?
 「2025年の崖」対策は、レガシーシステムを刷新する「守り」と、DXを実現する「攻め」の両立がカギとなります。
「2025年の崖」対策は、レガシーシステムを刷新する「守り」と、DXを実現する「攻め」の両立がカギとなります。
守りの対策
まずは業種に関係なく、レガシーシステムへの向き合い方を改めるところから始めましょう。DXレポートが発表された時点で、政府主導により問題意識や対応策を共有する流れはでき始めています。 大枠でいえば、経営層がレガシーシステムの現状を把握・見える化し、現行システムを刷新する体制を強化する姿勢を示すのが重要です。 以下、製造業で主要とされるシステムには注意を払いましょう。- 各社の基幹系業務をつかさどるERP
- 生産・流通系に特化したサプライチェーンマネジメントシステム(SCM)
- 製造現場におけるNC工作機械を制御するNCプログラム
- 産業用ロボット用ティーチングプログラム
攻めの対策
同時に、DX実現に向けた人材育成やガイドライン作成、共通プラットフォームの構築を積極的に行っていかなければなりません。 レガシーシステムを刷新しつつ、デジタル社会の基盤強化を同時に達成しなければ、「2025年の崖」が回避できないでしょう。 製造業においてどのような取り組みをすべきなのでしょうか。それは、製造業と深く関わるDX技術に対する情報収集と積極的な投資です。 例えば、以下のような先進技術がDXに欠かせない存在と言えるでしょう。- デジタルツイン
- IoT
- Al
- ブロックチェーン
- 5G通信