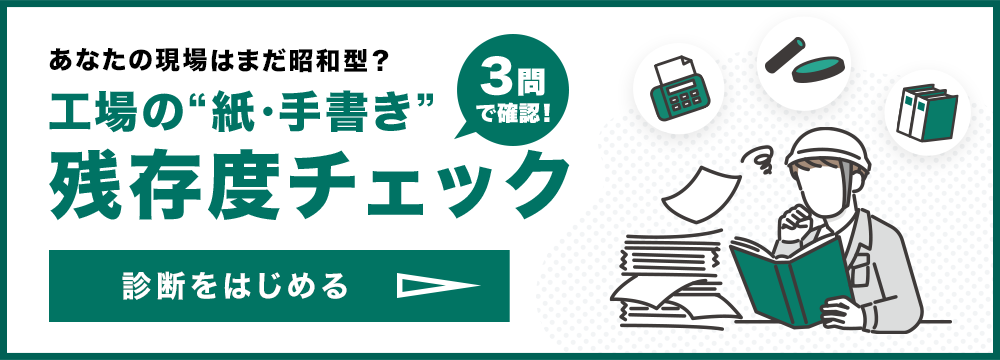目次
SFコンテンツが未来を形づくる。
漫画『鉄腕アトム』や『ドラえもん』などで描かれていたような自律汎用型ロボットはできるきざしがみえません。一方で、現実を拡張するARグラスはすでに市場展開されており、空飛ぶクルマも近い将来にサービス化する展望がみえてきています。小説やゲームなど、架空の物語で展開される近未来の構想が、現実世界のソリューションとして研究され、いずれは誰もが使えるサービスとして展開されるというのは、実はよくある話です。
VR空間内に五感を接続して、意識全体をその世界に入りこませる「フルダイブVR」も、そんなゲームや映画といったSFプロトタイピングから進んでいる研究領域のひとつだといえるでしょう。
この「フルダイブVR」は、現時点でどこまで研究が進んでいるのでしょうか。本記事では、フルダイブVRが注目されるようになったコンテンツを紹介したうえで、現時点での研究内容と、民間企業による取り組みを解説していきます。
フルダイブVRを表現したエンタメコンテンツ
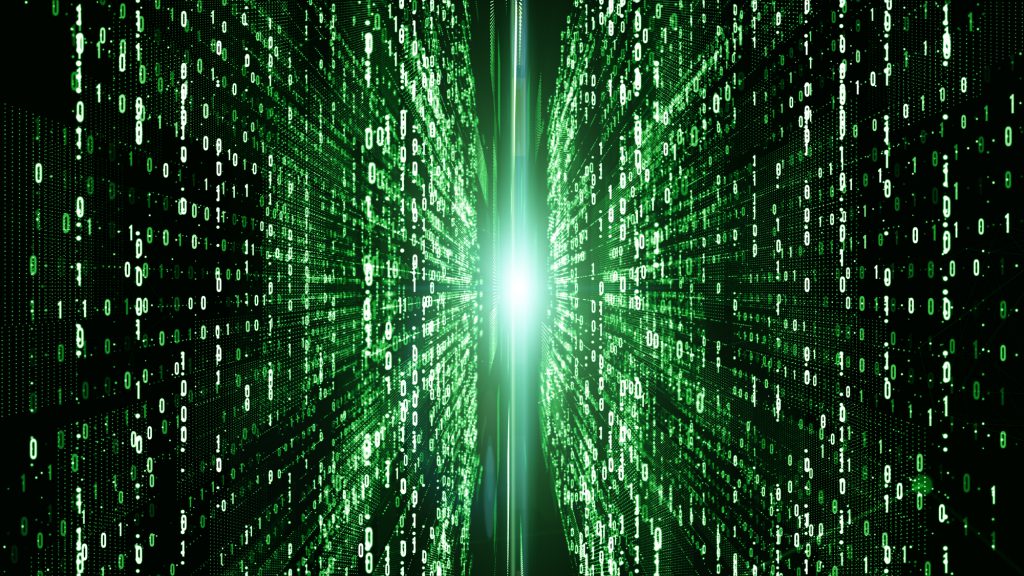
フルダイブVRでは、ユーザーは一般的なゲームで必要なコントローラーを使わず、現実世界で身体を動かす要領で、頭で考えることでVR空間内のアバターを操作することができるようになることが目指されています。その概念自体は、ずいぶんと前から提唱・研究されているものです。
言葉だけだとイメージしにくいため、実際に映像として表現されたコンテンツをご紹介します。
フルダイブVRのディストピアを描いた映画『マトリックス』
フルダイブVRを、誰もがイメージできる形で表現した有名な作品としては、1999年に劇場公開された映画『マトリックス』があげられるでしょう。
同作品では、大多数の人々は培養カプセルに閉じ込められており、後頭部からプラグを挿すことで、仮想現実へと意識を没入させ、さも現実世界かのように日常生活を過ごしています。明るい未来とは対照的なディストピアとして描かれています。
VRといっても、現在のようなHMD(ヘッドマウント・ディスプレイ)などが登場するわけではなく、後頭部のプラグから直接意識へと接続されている点が、五感もろともをフルダイブさせるイメージを体現しているといえるでしょう。
なお、同じように現実世界から仮想空間へと意識が没入する作品として、1982年に劇場公開された映画『トロン』や、2010年に劇場公開された同作品の続編映画『トロン:レガシー』があげられます。しかしこちらは現実世界の肉体そのものが物質電子変換装置によって作品内のゲーム空間に移転してしまうため、厳密にはフルダイブVRとは異なる概念となります。
「フルダイブ」注目のきっかけとなったライトノベル「SAO」
ここまでお伝えしたフルダイブVRの「フルダイブ」という言葉が注目されるきっかけになったのが、ライトノベル「ソードアート・オンライン」、通称「SAO」です。
SAOのストーリーは、世界初のVRMMORPGである「ソードアート・オンライン」に意識を接続した参加者たちが、仮想空間世界にて生死をかけたバトルを繰り広げるというもの。自発的にはログアウトすることができず、ゲーム内の死が現実世界の死と直結している点が、先述したマトリックスと似ています。
ライトノベル自体は2002年に発表され、2012年7月からはTVアニメの第1期が放送開始。その後第2期・第3期と続き、また2013年にはゲーム化もされるなど、多くのファンを獲得した作品となりました。
作品が注目されたことで、フルダイブVRの概念も、知れわたっていくことになりました。
フルダイブVRが実現するための要件

ここまでお伝えしたとおり、フルダイブVRは「視覚・聴覚・触覚・味覚・嗅覚」という五感すべてが、仮想空間へと没入することになります。
仮想空間への没入を実現するためには、以下3つの要件が必要だといわれています。
- 仮想空間内のアバターが感じる五感を、操作者の脳へとフィードバックする機能
- 操作に必要な感覚以外をシャットアウトする機能
- 脳からの出力信号を操作データに変換して、仮想空間内のアバターを操作する機能
1は脳へのインプット処理、2は脳とアバター間の調整処理、そして3は脳からのアウトプット処理ということで、脳を軸にした「インプット・処理・アウトプット」という、一連のシステムプロセスとしての要件が必要であることがわかります。
教育機関でのフルダイブVR研究

このフルダイブVRは、どこでどのような研究がなされているのでしょうか。以下、2つの代表的な国内研究をご紹介します。
「触原色」原理の応用(東京大学高齢社会総合研究機構 舘研究室)
舘暲(たち すすむ)東京大学名誉教授が主宰する「舘研究室」では、盲導犬ロボットやVR、テレイグジスタンスなど、分身ロボットもしくはアバター領域を40年以上にわたって研究されています。テレイグジスタンスとは、人間がロボットを自分の代理・分身として利用するという概念です。
さまざまな研究のなかで同研究チームは、「触原色」原理と呼ばれる、汎用的な方法で計測・伝送・提示可能な情報メディアとしての触覚のコンセプトを応用。まるで多くのものを「実際に手で触れている」かのような体験ができる技術の開発に成功しています。
通常の触覚経験とは違う、物理的に離れた場所での感覚体験は、フルダイブVRの実現に向けた大きな一歩であるといえるでしょう。
舘名誉教授によるテレイグジスタンスの最初のアイデア内容(1980年当時)を描いた動画が以下となります。
ブレイン・マシン・インターフェース臨床試験(大阪大学医学部付属病院 未来医療開発部 未来医療センター)
大阪大学医学部付属病院 未来医療開発部 未来医療センターでも、考えただけで機械を動かすことができる技術の研究を進めています。
具体的には、脳信号をコンピューターで解読して、身体が全く動かない人であっても、ロボットや電化製品などを意のままに動かせる技術「運動型ブレイン・マシン・インターフェース(BMI)」です。脳を傷つけることなく、シート状の電極を使うだけで、脳表脳波を計測・解読し、考えたとおりの動きを外部データとして出力することに成功しています。
現時点では、電極からコードが体外に出たままの状態であることが留意点となりますが、以降の段階では「完全埋め込み型ワイヤレスシステム」の開発を進め、自宅でも広く使用できるものとしての想定がなされていることから、BMIおよびフルダイブVRの民主化にとっての重要な取り組みだといえます。
民間企業での取り組み

最後に、民間企業での取り組みについて、2社の事例をご紹介します。
Telexistence株式会社
Telexistence株式会社は、先ほどご紹介した舘暲名誉教授が会長を務めるITベンチャーです。
同社は2020年7月に、遠隔操作ロボット技術を核にした「Augmented Workforce Platform(拡張労働基盤)」の構築を可能にする半自律型遠隔操作ロボット「Model-T」を発表しました。具体的には、小売業界のなかでも作業工数が大きく、人間への負担も大きい「商品陳列業務」を遠隔化・自動化するソリューションとして発表したのです。
2021年10月からは、経済産業省「ロボット実装モデル構築推進タスクフォース」の一環としてファミリーマートへの遠隔操作ロボットの導入が予定されており、店舗の省人化や物理的な店舗立地に制約されない、自由度の高いスタッフ採用が期待されています。
Neurable社
米国のスタートアップであるNeurable社は2017年に、脳とコンピューターをつなぐBCI(ブレイン・コンピュータ・インターフェース)システムを開発しました。このシステムは同年7月30日〜8月3日にかけて開催されたCG技術などを紹介するカンファレンス「ACM SIGGRAPH(シーグラフ)」で発表され、具体的には、「The Awakening」と呼ばれるVRゲームでの活用を想定しています。
独自開発したVR-HMD「HTC Vive headset」を装着することで、利用者の脳活動状態をモニタリングし、その結果をデータとして返して、仮想空間内でオブジェクト(対象物)を拾ったり投げたりすることができるようになっています。
先述したテレイグジスタンス技術が現実のモノを想定したAR的なフルダイブ技術だとすれば、BCIは仮想空間を前提にした、よりSAO的なフルダイブVRであるといえるでしょう。
2030年にはフルダイブVRが実現する?
以上、今回は「フルダイブVR」研究について、現時点での研究内容と、民間企業による取り組み内容をご紹介していきました。
まだフルダイブとはいえない「ハーフダイブ」、いや「クォータダイブ」くらいの技術状況ではありますが、かのレイ・カーツワイル氏の説では、2030年にはフルダイブVRが実現するといわれています。
あと10年もしないうちに、マトリックスやSAOのような世界観が実現するかもしれないと思うと、ワクワクしてくるのではないでしょうか。